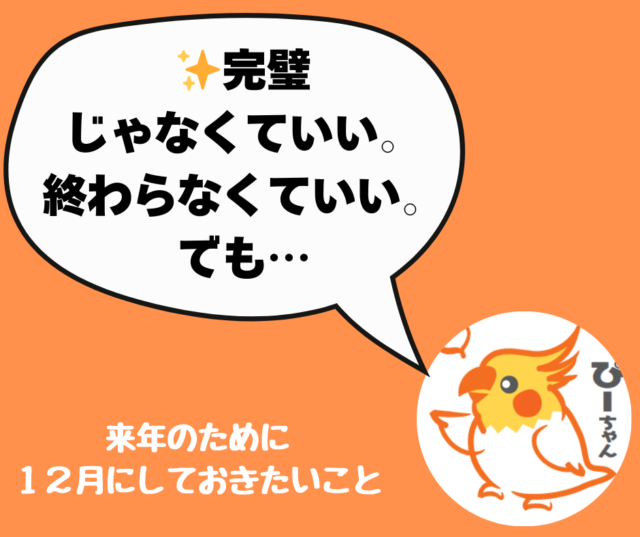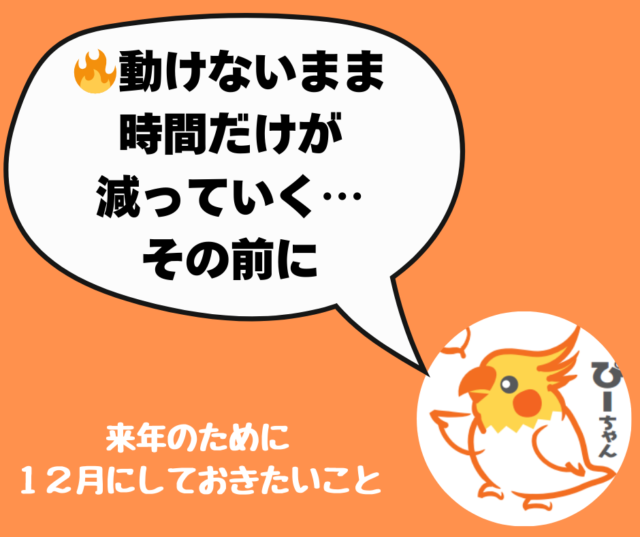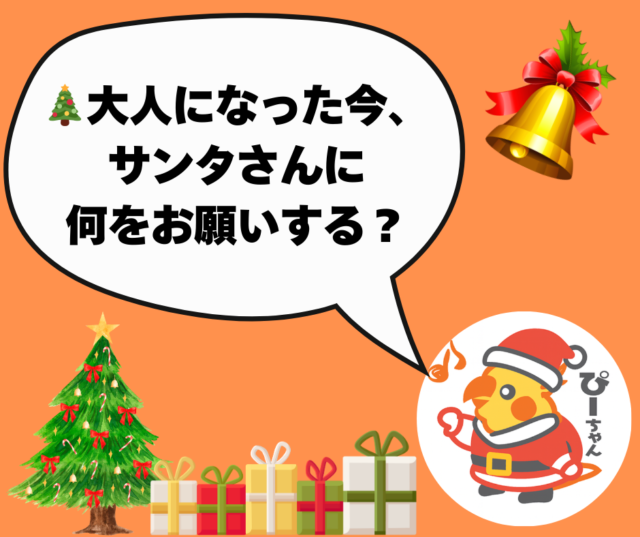
こんにちは、ファイナンシャルプランナーのぴーちゃんです🐥
クリスマスが近づくと、子どもの頃の気持ちをふと思い出します。
サンタクロースに何をお願いしようか、胸を弾ませながら考えた夜。
でも大人になると、いつの間にか
「お願いする」こと自体を忘れてしまいがちです。
けれど、本当は――
大人だって、サンタさんにお願いしていい。
もし今、願いをひとつ叶えてもらえるとしたら、
あなたは何をお願いするでしょうか。
ピカピカの新車?
たくさんのお金?
病気をしない健康な体?
それとも、減らない“時間”?
どれも魅力的で、どれも間違いではありません。
でも、少し立ち止まって考えてみてほしいのです。
「それを手に入れたら、私はどんな一年を過ごしたいんだろう?」と。
お金があっても、心が疲れていたら幸せは感じにくい。
時間があっても、使い方がわからなければただ過ぎていくだけ。
だから、来年を素敵な年にするための本当のプレゼントは、
“モノ”ではないのかもしれません。
たとえば、
自分を大切にできる心の余裕。
一歩踏み出す勇気。
失敗しても笑い飛ばせるしなやかさ。
毎日をちゃんと味わえる時間の使い方。
そんな目に見えない贈り物こそ、
一年を通してあなたを支えてくれるはずです。
今年のクリスマス、
子どもにプレゼントを用意しながら、
ぜひ自分にも問いかけてみてください。
「来年の私を幸せにするために、
サンタさんに何をお願いしよう?」
答えを考える時間そのものが、
もうすでに素敵なプレゼントなのかもしれません🎄✨
最後までお読みいただきありがとうございます。