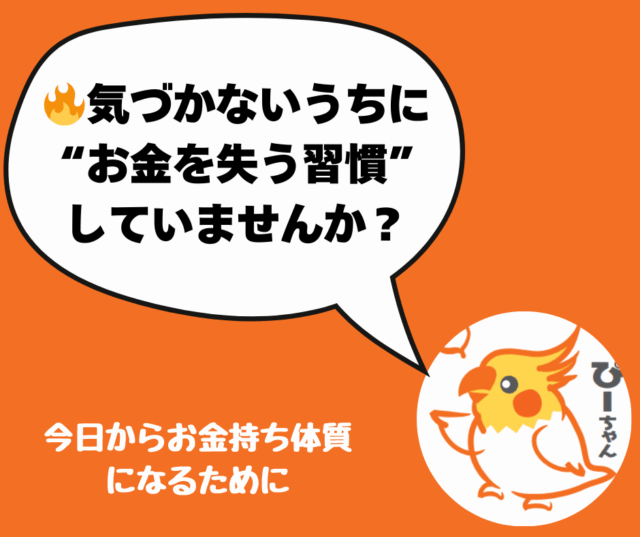オンラインにて子育てファミリーの家計相談をおこなっている 塙 です。
梅雨があけたと思っていたら、連日の雨で戻り梅雨ですね。
コロナウィルスの感染も過去最大を記録しそうな勢いです。
感染防止に気を付けながら、体調管理に気をつけて、過ごしましょう。
ここ数年の日本は、異常気象の影響で自然災害が多くなり、台風や集中豪雨による水災の被害が増えています。
火災保険の水災補償は、多くの方が加入していますが、なかには加入していない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

水災補償は、大雨や河川の氾濫による浸水などの被害に対しての補償です。
最近では、集中的に激しい雨が降り、河川の氾濫や土砂災害などの被害の危険性が高まっています。
水災補償は、水災の損害を補償するものです。
例
集中豪雨で自宅が床上浸水した。
豪雨で土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。
また水災には、支払い基準があり、基準以上の損害の場合に保険金が支払われます。
床上浸水もしくは地盤面より45㎝を超える浸水、もしくは再調達価額の30%以上の損害が発生した場合といった基準がもうけられています。
水災補償が必要ないという場合には、ないプランを選ぶことで、保険料を抑えることもできます。
自宅の状況を考えずに、保険料を安くするために水災補償のないプランを選択することはやめましょう。
ご自宅の場所をハザードマップなどでしっかりと確認をしてから、プランを選択しましょう。
特約なども各保険会社によって、いろいろなものがあります。
東京海上日動火災保険株式会社より「水災初期費用補償特約」の発売が予定されています。
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/release/pdf/220530_02.pdf
豪雨や土砂災害に伴う水災による損害を受け、保険金が支払われる場合に、当座の生活資金として10万円を早期に支払うという特約です。
今年の10月以降に、火災保険料が値上がりすることが予想されます。
加入している火災保険、地震保険の保障内容を確認し、今のうちに見直しをおこないましょう。
過去の改定の際に、火災保険の見直しを行い補償の追加、適用可能な割引がある場合は、利用するなどされた家庭も多くあります。まだ、補償内容を確認したことがないという方は、一度ご自宅などの火災保険の証券を確認してみましょう。必要であれば見直しを検討しましょう。
最近では、地震だけでなく、台風や爆弾低気圧などによる水害、風災、雪災が多くなっています。
地震、台風など多くの自然災害リスクがあります。
住んでいる地域の避難場所の把握や、いざというときの持ち出し品の準備、避難せず自宅にて待機の場合は、家族の人数分の水や食料の確保は、各自にて可能なことです。
コロナウイルスの感染防止対策のための自粛や、感染してしまった場合、濃厚接触者になってしまった場合などを考えて、備蓄をすることも当たり前のようになってきました。
災害の避難時に持ち出すものは、現金、身分証明書、着替え等ですが、各家庭の状況によっては、さらに準備が必要となります。
備蓄品は、一般的に家族の人数分かける7日といわれています。
非常食などは基本的に期限が長いものが一般的ですが、念のため確認をして、期限切れなども防ぐようにしましょう。
ご家族状況により、備えるものがあるので、時間にゆとりのある時に、リストアップしてみましょう。なにかあってからではなく、常日頃から備えていれば、万が一のときに落ち着いた行動ができます。
以下のサイトなども参考にしてみてください。
総務省消防庁 地震防災マニュアル
https://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_manual/too/tool.html
防災グッズリストダウンロード (NHK)
http://www.nhk.or.jp/sonae/goods/index.html

非常用品の確認
懐中電灯、携帯用ラジオ、乾電池、救急用品、衣類、非常用食品、携帯ボンベ式コンロ、貴重品、携帯電話充電器
室内からの安全対策
飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼る。台風の際は飛来物に備えてカーテンやブラインドを下ろしておく
水の確保
断水に備えて飲料水を確保。浴槽に水を張るなどして生活用水を確保する。
避難場所の確認
学校や公民館など、避難場所と指定されている場所への避難経路を確認しておく。
普段から家族で避難場所や連絡方法などを話し合っておく。
非常持ち出し品の例
飲料水、乾パンやクラッカーなど、レトルト食品、缶詰、粉ミルク、哺乳瓶。
救急医薬品、常備薬、マスク、生理用品、紙おむつ。
現金(小銭も)、預金通帳など、印鑑、健康保険証、身分証明書。
下着、タオル、寝袋、雨具、軍手、靴。
ナイフ、缶切り、鍋、水筒、懐中電灯、ラジオ、電池、ロープ、マッチやライター、使い捨てカイロ、ティッシュ、筆記用具、ゴミ袋。
防災頭巾やヘルメット、予備の眼鏡、地図
度重なる災害やコロナ禍で、非常食などの備蓄に対する意識は、高くなっています。
災害時だけでなく、コロナによって自宅療養になってしまった場合も想定して、備蓄をしている家庭がほとんどのようです。
体調が悪くなったとき、発熱や喉の痛みなどの風邪症状や下痢などの胃腸症状がでたときを想定し、食欲がなくても食べられるもの、必要な栄養素を補えるもの、長期保存が可能なもの、自分が好きな食べ物を揃えておきましょう。
また、新型コロナウイルス感染症になってしまった場合、発熱や倦怠感などにより調理が困難になることが想定されます。
調理を必要としない開封するだけで食事ができる缶詰、加熱するだけで調理できる食品(冷凍食品やレトルト食品)なども一定数備蓄しておくことが大切です。
そして、食べなれていない食品よりも、日頃から食べなれた食品を備蓄することも大切です。
ご家族が感染してしまい、自宅療養が必要になった場合、トイレや洗面所、廊下やドアノブなどの共有スペースは感染リスクが高まります。
衛生用品を多めに準備しておく必要があります。
こまめに消毒をする必要があるので、アルコール消毒液やゴム手袋などもあわせて備蓄しておきましょう。
家族間での感染拡大を予防するため、マスクを着用して生活することも重要です。
汚れたらこまめに替えることができるよう、不織布マスクも備蓄しておきましょう。
これらの衛生用品も多めに備蓄しておき、開封したら、在庫がなくなる前に購入しておきましょう。
一時期のように、マスクが手に入らないということはないですが、在庫を切らさないように意識しましょう。
療養を想定した備蓄品
ゼリー飲料、常温保存できるカップゼリー、フルーツゼリー
パックご飯、レトルトパウチのおかゆ
常温で長期保存可能なゆで麺、冷凍うどん、冷凍ごはん
卵スープ、春雨スープなど具だくさんで食物繊維がとれるフリーズドライのスープ
焼き鳥缶、いわし味付缶、サバの水煮缶、ツナ缶、大豆水煮
果物缶、スープ
自然災害を完全に防ぐことは、不可能なことですが、できる限りの備えは必要です。ご自身とご家族を守るためにも、常日頃からできる限りの備えはしておきましょう。
またコロナウイルスの感染も、過去最大の感染規模になるおそれがあると言われています。
いつかかってしまっても、おかしくはない状況です。
体調に異変を感じてから、あわてるのではなく、自宅療養する場合も想定して備えておきましょう。
塙
株式会社Switppyでは、家計管理や保険についてのお金の話をメルマガにて配信させていただいております。是非メルマガのご登録をいただければ幸いです。ご登録をいただくと、『みっちゃん家隠れ赤字脱出作戦』(PDF)と家計管理ができる家計簿(Excel)をプレゼントいたします。家計簿は、バームスコーポレーション有限会社さま作成のものです。家計簿をご利用いただける環境はパソコンのみとなっております。iPad等では、現在ご利用ができないことをご了承ください。ご希望される方は、下記の登録フォームよりご登録をお願いいたします。
あなたの家計は隠れ赤字の心配はないですか?ご登録は下記の登録フォームよりお願いいたします。