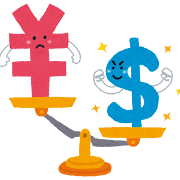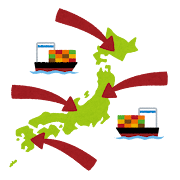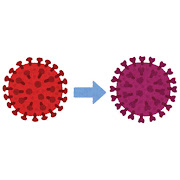オンラインにて子育てファミリーの家計相談をおこなっている 塙 です。
ゴールデンウイークがあけてから、もう梅雨入りかと思うほど、雨の日が多いですね。気温の変化のため、体調などを崩さないように過ごしましょう。
最近は、いろいろなものの値上がりのニュースばかりです。

食品や生活必需品の値上げは、家計管理に直接影響があるので、少し気を引き締めないと、家計のバランスをくずすきっかけになります。
普段から、家計管理をされている方は、予算管理をしっかりおこなっています。どこかの支出が上がってしまう分を、他の支出を抑えるなどして、収支バランスを保つことを行っています。
食品も、電気ガスも必要不可欠なものです、
今まで通りに必要だから、欲しいものだからと消費を続けてしまうと、赤字家計になってしまいます。
資源も限りがあります。
食費をおさえるために、質をおとしてしまったり、過度な我慢をすることは、健康によくありません。
ご家庭によって、食費の予算は異なります。食費や日用品よりもっと大きな割合を占めている住居費や保険料など家計のうちでもっと大きな割合を占めているものを見直すと、それより小さい食費、日用品を過度に節約する必要はなくなります。
住居費に比べると、保険料は比較的見直しがしやすい項目です。
生活や家族構成、年齢などが変わっているのに、以前の状況で加入をしたままのものはありませんか?
また、今では不要な保障や、逆に必要な保障などはないでしょうか?
少し補いたい場合などに利用しやすい少額短期保険という保険があります。
少額短期保険とは、一定の事業規模の範囲内において保険金額が1,000万円以下に定められている保険商品のことをいいます。
保険金額に上限が設けられていることから一般的な保険商品に比べて毎月の保険料が安めに設定されていることが多く、保険料を抑えつつ上記のような特定のニーズにおける必要最低限の補償を備える目的で加入されています。
少額短期保険業に係る保険金額
少額短期保険業では、次のとおり保険の区分に応じて1被保険者について引受ける保険金額の上限が設けられています。なお、1~6の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となります。
1.死亡保険 300万円以下
2.医療保険(傷害疾病保険)80万円以下
3.疾病等を原因とする重度障害保険 300万円以下
4.傷害を原因とする特定重度障害保険600万円以下
5.傷害死亡保険 傷害死亡保険は、300万円以下
(調整規定付き傷害死亡保険の場合は、600万円)
6.損害保険 1,000万円以下
7.低発生率保険 1,000万円以下
少額短期保険と生命保険・損害保険との違い
少額短期保険
保険金額は最大で1,000万円まで
保険期間が1年間または2年間
人が生存することを条件とした保険金支払いができない
積立型の保険や満期返戻金のある保険商品も引き受け不可
生命保険、損害保険
一般的な保険商品では数億円以上の保険金を設定することも可能
一般的な保険商品は定期保険でも10年、終身保険なら一生涯の保障
| 生命保険会社 | 少額短期保険業者 | |
| 監督官庁 | 金融庁 | 金融庁 |
| 設立時の免許制 | 免許制 | 登録制 |
| 公的セーフティーネット | あり | なし |
| 重要事項説明義務 | あり | なし |
| 保険金額の上限 | 認可による | 1被保険者について、一定の条件を満たし、総額1,000万円以下 |
| 保健期間 | 認可による | 生命保険と医療保険は1年損害保険は2年 |
| 保険契約者保護機構 | 加入義務あり | なし 最低1,000万円を法務局に供託する義務がある。 |
少額短期保険に払い込む保険料は掛け捨てなので、満期保険金や解約返戻金のように保険料が返ってくるような仕組みは採用されていません。
少額短期保険で扱えない分野
人が生存することを条件とした保険商品(貯蓄保険など)
積立型生命保険などの満期を迎えた際に返戻金が受け取れる保険商品
(養老保険や学資保険など)
個人年金保険などの1年以上の定期的な保険金支払いがある保険商品
外貨を取り扱う保険商品
少額短期保険のデメリット
*少額短期保険は、生命保険や医療保険などに比べて保障の範囲が限定的です。
特定のニーズに特化した保険商品であっても必ずしも万能な商品ではありません。
*少額短期保険は、保障金額が最大で1,000万円に抑えられています。
そのため、一般的な生命保険や損害保険に比べると保険金が不十分な場合もあります。
特に、少額短期保険での死亡保障は最大で300万円です。通常の死亡保険では倍以上の保険金が支払われるケースがほとんどです。
少額短期保険の契約を検討する際は、通常の生命保険や損害保険を契約した上で、不足分を補うことを目的にしましょう。
*少額短期保険では、保障期間が1年間または2年間までです。
満期を迎えた際には再契約することも可能ですが、その際の保険料はその時点での年齢により計算されます。長期的な保障をしっかり検討したい場合には、少額短期保険はおすすめできません。
*保険会社が破綻した場合の契約者補償がない
保険契約者保護機構の補償対象外となっているため、仮に保険会社が経営破綻をした場合は補償が受けられません。
そのため、供託金積立制度やソルベンシー・マージン比率の適切性、その他資産運用における様々な規定を設けて契約者の保護を図っています。
保険会社が破綻すると、契約に影響がでます。そのため、保険会社が破綻した場合の資金援助や契約者保護の目的で保険契約者保護機構があります。
外資系も含め、日本で営業をする保険会社は、生命保険契約者保護機構か損害保険契約者保護機構に加入しなければいけません。
共済と少額短期保険業者は対象外です。
保険会社が破綻した場合の保険契約の保護の内容は、生命保険契約については、原則、全契約の責任準備金の90%です。
損害保険契約については、保険の種類ごとに異なります。
補償されるのは、破綻時点での責任準備金の90%であるため、契約引継ぎの際に、予定利率等の基礎率が見直されると更に、保険金等が減額されます。
*保険料は掛け捨てです。
保険料が安いことが特徴ですが、保険料は掛け捨てです。
*少額短期保険の保険料は生命保険料控除の対象外です。
少額短期保険のメリット
*特定のことに特化した商品が多い
葬儀保険、レスキュー費用保険、ネットトラブル保険、モバイル保険など。
通常の保険ではカバーされないような特定のニーズに特化した保険商品があります。
*日常のありがちなリスクに費用を抑えてそなえることができる。
毎月の出費を抑えつつ、日常生活での少しの不安に対して備えることができます。
*少額短期保険の保険期間は1年間または2年間に設定されているので、短期間だけ補償が欲しい場合に便利な保険商品です。
通常の定期保険では最低でも5年、10年以上の保険期間が設けられていることが多く、その分だけ払い込むことになる保険料が多くなります。
少額短期保険なら、目的の期間だけ契約することができます。ライフプランにあわせて、必要な期間だけ加入することで、必要のない期間の保険料を負担する必要がなくなります。
*加入済みの保険で少し足りない不安な部分を補う。
少額短期保険を検討する際には、すでに加入している保険に足りない部分を補うということを考えてみましょう。
現在、加入しているものを解約して、保障、補償を大きくして加入しなおす場合と、追加で契約をする場合、少額短期保険で加入する場合と比較してみましょう。
少額短期保険を上手に活用することで、少ない保険料で保障、補償を手厚くできるかもしれません。
希望するあと少しや、欲しい保障、補償が割安で備えることができ、上手に利用することで、家計の保険料をおさえることができるかもしれません。
塙
株式会社Switppyでは、家計管理や保険についてのお金の話をメルマガにて配信させていただいております。是非メルマガのご登録をいただければ幸いです。ご登録をいただくと、『みっちゃん家隠れ赤字脱出作戦』(PDF)と家計管理ができる家計簿(Excel)をプレゼントいたします。家計簿は、バームスコーポレーション有限会社さま作成のものです。家計簿をご利用いただける環境はパソコンのみとなっております。iPad等では、現在ご利用ができないことをご了承ください。ご希望される方は、下記の登録フォームよりご登録をお願いいたします。
あなたの家計は隠れ赤字の心配はないですか?ご登録は下記の登録フォームよりお願いいたします。