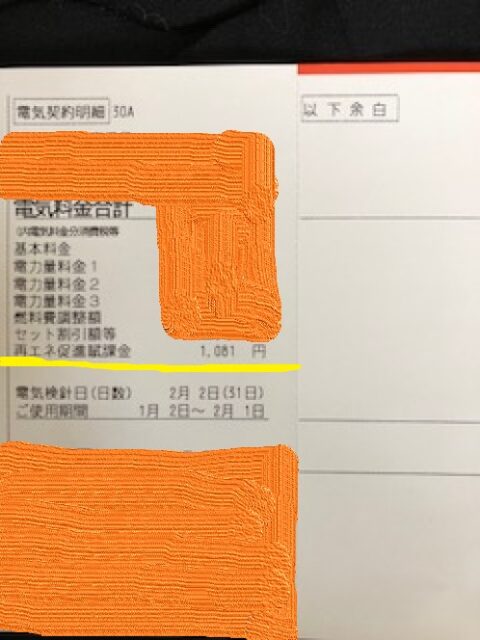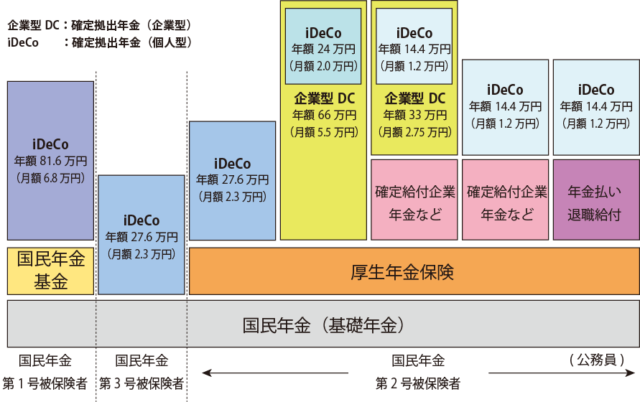オンラインにて子育てファミリーの家計相談をおこなっている 塙 です。
朝晩は、まだまだ肌寒い日が続いていますが、日中は汗ばむ陽気になってきましたね。
コロナウイルスの家計への影響は、どの家庭でも感じていらっしゃることかと思います。
収支の変化、生活スタイルの変化で家計の見直しをされた方も多くいらっしゃることでしょう。
新年度をむかえて、お子様の将来の教育費の準備について考える時期でもあります。
教育費の準備は、どのような方法があるか、考えてみましょう。

児童手当
児童手当は需給の条件を満たすご家庭で、0歳から中学を卒業するまで受給可能です。すべて貯蓄することができれば、まとまった資金になります。
家計相談のなかでも、「児童手当はそのまま貯めてくださいね。」とよくお話させいただいています。
例えば0歳から3歳未満まで15,000円、3歳から小学校修了まで10,000円(第一子と第二子)、中学校卒業まで10,000円の場合、これらの手当をすべて貯蓄できた場合、約200万円の資金をつくることが可能です。
預貯金
毎月の家計のなかから、コツコツと貯める。
この際、無理なく貯めることも大事ですが、将来いくら必要になるのかを考えて、そのためには、毎月いくら貯めなければいけないのかを考慮し貯蓄額を決めましょう。毎月貯める金額を一定にすることができれば、計画通りに目標額を達成することが可能です。
預貯金の方法は、普通預金に預けるだけの方法もありますが、教育資金を貯めるのに向いているのは積立定期預金や自動定額積立預金です。毎月自動的にお金を積み立てられるので、効率的です。
メリットは元本が保証されていることと流動性が高いことです。
もしも、銀行が破綻した場合でも「預金保険制度」によって、1,000万円までは預金は保護されます。
デメリットは、お金が増えることはほとんどないところです。
また流動性があるがゆえに、貯まったお金をつい取り崩してしまうことがありえます。コロナウイルスの影響で、今後家計への影響がさらに悪化するかもしれません。生活をすることが最優先なので、万が一の場合は、取り崩すことも否定できませんが、なにもないときにも、取り崩してしまうと、目標額を貯めることができなくなってしまいます。
期間の長い定期預金等を利用することを検討しましょう。
学資保険
教育資金を貯めるための貯蓄型保険商品のことです。
学資保険は、契約者に万が一のことがあった場合、それ以降は保険金を支払う必要が無くなり、そのうえで祝い金や満期保険金を受け取れるという特徴があります。
メリットは、万が一のときに備えられる保険商品であるということです。契約者が死亡したり、重い障害を抱えたりした場合、それ以降の保険料は支払い免除となり、さらに祝い金や満期保険金は保証されます。
学資保険は、貯金とは異なり流動性がないため、ほぼ強制的に教育資金を確保できます。
商品によっては、貯蓄するよりは少し高い利率(返戻率)のものもあります。あまり増えないものでも、学資保険はあくまでも保険商品です。保証を備えつつ貯蓄をすることが可能です。また所得控除の一般生命保険料の対象になります。
デメリットは、流動性がないことです。もしも途中解約した場合、返戻金が、支払った保険料の総額よりも低くなってしまいます。また、すべての教育資金を学資保険で賄おうとすると、いざという場合に対応しきれない可能性があるため、他の運用手段と分散して貯めるなどの工夫も必要です。
学資保険は契約時に決定した保険料を毎月支払い、利率が変動することがありません。そのため、インフレが発生した場合に祝い金や満期保険金が契約当初と同様の価値ではなくなるケースもあります。
インフレリスクとは、物の価値が時間とともに上がっていくことによるリスクです。
18年後の300万円が今の300万円と同じ価値とは限らないということです。
例えば、大学進学の費用にと考えていても、インフレによって入学費や学費が値上がりすると、学資保険の保険金だけでは足りなくなることがあります。
また、学資保険の資金を祖父母がだしてくれるケースでは税金の面で注意が必要です。契約者が祖父母で受取人がお子様の場合、贈与税が課税されます。契約者が親でも同じです。契約者と受取人は同一の方が税制面では無難です。この場合は、一時所得の対象となりますが、贈与税に比べると、課税額は抑えられます。
低解約返戻金終身保険
保険料を払い込む期間の解約返戻金の金額を通常の終身保険より低く設定することで、保険料の総額を割安にした保険のことです。保険料の払い込みが終了した後は、解約返戻金の水準が通常の終身保険と同じになります。
子どもが学資保険に入れない年齢であっても、条件次第で加入できるというのもメリットとなります。その分、月々の支払額は高くなってしまいますが、教育費を貯める選択肢のひとつの方法になります。
学資保険の代わりに利用する方も多くいらっしゃいます。
メリットは、プランや条件によっては、学資保険よりも返戻率が高くなることです。さらに、学資保険と同じように、契約者に万が一のことがあった場合に払い込み免除、保険金の満額受け取りが可能になる特約がついている商品が多く存在します。
そして、子どもが進学せずに就職した場合や、その他の事情で必要がなくなってしまった場合に、ご自身の老後資金のための貯蓄や死亡時の保険など、利用目的を変更できるというのも低解約返戻金型終身保険のメリットです。
用途を限定せずに目的を選ぶことが可能な保険商品ですので、幅広い目的で貯蓄したいという方にはお勧めです。
デメリットは、途中解約した場合の返戻金を少なくして保険料を割安にしている点です。途中で解約してしまうと返戻金が少なくなる可能性があります。
また、加入時の条件によっては返戻金が少なくなることもあります。そのため、教育資金を低解約返戻金型終身保険で貯める場合は、複数の設計プランを比較するなど、各保険会社の商品をいろいろ検討する必要があります。
そして、契約者の健康状態によっては、低解約返戻金型終身保険に加入できないケースもあるため注意が必要です。
投資信託
元本が保証されるわけではないため、あくまでも他の方法と併用をしつつ、投資信託を利用することを検討しましょう。
メリットは、投資信託は資産運用のプロが、運用するという点です。運用で発生した利益は基準価額の上昇や分配金として投資家に還元されます。
投資信託ではさまざまな資産に分散投資ができ、個別株や債券への投資に比べると投資リスクを抑えられます。保険と同様に運用をプロに任せられるため、投資の知識に自身がなくても利用が可能です。しかし、大切なお金を預けるので、まったく把握をしないことはリスクです。
運用成績や投資対象については月次や年次で運用報告書・レポートなどで詳細に確認することが可能です。ご自身で確認しやすいと安心ですよね。
また、投資信託は運用を専門家に委託します。そのため、信託報酬などのコストが発生します。投資信託を選ぶ際はコストの内容をよく確認しましょう。
デメリットは、元本保証がないということです。投資信託は比較的リスクを抑えられる投資方法であるものの、運用成績によっては損失が発生することがあります。
教育資金のすべてを投資信託で準備するのではなく、他の方法と併用することをお勧めします。
必要な時期がせまってからあせることのないように、ゆとりをもって計画をたてましょう。また、教育資金の準備の方法は、ご自身の家庭にあった無理のないものを選びましょう。
塙
株式会社Switppyでは、家計管理や保険についてのお金の話をメルマガにて配信させていただいております。是非メルマガのご登録をいただければ幸いです。ご登録をいただくと、『みっちゃん家隠れ赤字脱出作戦』(PDF)と家計管理ができる家計のCF表(Excel)をプレゼントいたします。CF表は、バームスコーポレーション有限会社さま作成のものです。CF表をご利用いただける環境はパソコンのみとなっております。iPad等では、現在ご利用ができないことをご了承ください。ご希望される方は、下記の登録フォームよりご登録をお願いいたします。
あなたの家計は隠れ赤字の心配はないですか?ご登録は下記の登録フォームよりお願いいたします。